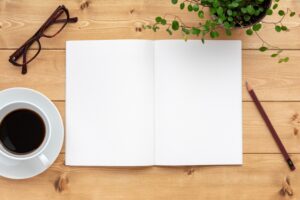「市町村のエンディングノートってどんなもの?」
「市販のものとの違いはあるのかしら」
終活が注目されてきている近年、自治体の負担軽減や連携を目的として、エンディングノートを発行する市町村が増えています。
内容は市町村によってさまざまですが、市販のものと比べると、要点を絞ったものが多いと言えます。
遺された家族にとってすぐに必要な最低限のことを、シンプルに書くことができるエンディングノートなのです。
市販のものとどちらがいいのか、どちらがより自分にあっているのか、気になるところですね。
この記事では、そんな市町村のエンディングノートの基礎知識を徹底的に解説しています。メリットとデメリットも分かるので、あなたにとっての使い勝手の良さも分かります。
<この記事を読めばわかること>
・市町村のエンディングノートの基礎知識
・市販のエンディングノートとの違い
・市町村がエンディングノートを配布する理由
・市町村のエンディングノートの形状別メリット&デメリット
・市町村のエンディングノートが向いている人
記事の最後には、おすすめの市町村エンディングノートと全国配布市町村の一覧を掲載しているので、エンディングノート選びの参考になさってください。
それではさっそく、市町村のエンディングノートについて詳しく解説していきましょう!
1. 市町村が作成するエンディングノートの基礎知識

エンディングノートとは、自分に万が一のことが起きたときのために用意しておく、家族など大切な人に想いや希望を伝えるノートのことです。
内容は、個人情報、資産、介護やお葬式・お墓についての希望やメッセージなど、多岐にわたります。
遺される家族の負担を減らしたり、生きているうちに自分の死を見つめることで、いまをより自分らしく前向きに生きようとするためのものでもあります。
では、市町村が作成するエンディングノートについては、何か特別な特徴や目的があるものなのでしょうか?
次の項から、具体的に見ていきましょう。
1-1. 市町村が配布するエンディングノートとは?
市町村で独自に作成し、一部の自治体を除いてほとんどが無料で配布しているエンディングノートです。
配布と合わせて、書き方セミナーなどを開催しているところもあります。
福祉課や高齢支援課などが担当部署となり、地域情報や相談窓口の案内の記載があることが特徴です。
それぞれの自治体が独自で作成しているため、内容や書き方、ページ数などがそれぞれで異なります。
意外に思われるかもしれませんが、市町村が独自にエンディングノートを作成して発行することにより、自治体としての処理を円滑にしたり、負担を軽減したりする効果があるため、いま全国で増えているのです。
また、初めての人でもスムーズに書き込めるようにと、書き込み項目を絞り込んでいるものが多いです。
例えば、書き込み項目には以下のようなものがあります。
・基本情報(氏名、生年月日、住所、本籍地、健康保険証やパスポートの番号など)
・資産のこと
・過去のこと(自分史、年表など)
・現在のこと(かかりつけ医や常用薬、好きなもの、趣味など)
・未来のこと(これからやりたいこと、目標など)
・いざという時のこと(介護、医療、延命処置の希望など)
・葬儀の希望
・お墓の希望
・相続の希望
・大切な人へのメッセージ
これらの項目の中から、市町村ごとに、作成の目的や市民の声を取り入れるなどによって、項目の取捨選択をしているのです。
1-2. 市販のエンディングノートとの違いは?
市町村がそれぞれで独自に作成しているものとはいえ、書くべき項目はそれぞれで備えている市町村のエンディングノート。
市販のものとの違いは、どんな部分に現れているのでしょうか?
1-2-1. ページ数
ページ数は総じて市町村のエンディングノートの方が少なめです。
市販のものは差別化のために書き込み項目が多岐にわたり、その分ページ数も多くなる傾向があるためです。
少ないページ数でも、市民にアンケートを取ったり制作委員を公募したりと、市民の声を反映し、本当に必要な項目を選りすぐっているものが多いと言えます。
1-2-2. デザイン
見た目やデザインは、好みもありますが、市町村のものより市販のものの方が装丁や表紙、中のイラスト装飾などのデザイン性がより高く、凝っていると言えます。
また、紙質についても、市販のものの方が厚みがあったり、表紙に光沢紙を使っているなど、お金のかかっている感じがあります。
1-2-3. 地域情報の掲載
先の項目でも述べましたが、市町村作成のエンディングノートは、自治体ならではの地域情報や、相談窓口の案内などがページ内や巻末に盛り込まれているものが多いです。
介護が必要になった場合に必要な地域包括支援センターの情報、医療の項目には公立病院の情報など、実際に困った時にすぐ相談できる先が掲載されているので心強いです。
また、無料配布を実現するため、地域の企業の広告を掲載していることもあります。
地域情報の掲載は、市町村のエンディングノートの一番の特徴と言えるでしょう。
1-3. 配布場所
もらえる場所は主に以下の2箇所ですが、自治体によってはどちらか一方しか行っていない場合もあります。
窓口での受け取りを希望される場合には、事前にご希望の自治体にお問い合わせください。
1-3-1. 担当窓口や指定の配布場所
役所の担当窓口のほか、地域包括支援センターやケアプラザ、社会福祉協議会のコミュニティサロンなどで配布されます。
自治体によっては、書き方セミナーの開催と同時に配布する場合もあります。
手渡しでもらえるエンディングノートは、背中心をホチキス止めで綴じた冊子型になっているものが多いです。
1-3-2. 公式ホームページからのダウンロード
公式ホームページで、エンディングノートのデータファイルを配布しているところも増えています。
PDFファイルを配布する自治体が多いですが、一部ではWordファイルを配布しています。
PDF版は自分で出力して手書きしますが、Word版であればキーボードで直接入力ができます。
どちらも自分で綴じる必要があります。
1-4. 入手条件
指定窓口で配布される冊子型の市町村のエンディングノートの入手条件は、基本的には以下の通りです。
・何歳からでももらえる
・マイナンバーや免許証の提示は不要
年代や性別、大まかな居住エリアなどについて、選択式のアンケートを求められる場合はありますが、回答内容によって配布を拒否されることはありません。
なお、データファイルのダウンロードはどの市町村のエンディングノートも無料で、環境さえあれば全国だれでも入手ができます。
| 【注意】
一部市町村では、作成部数の都合から、冊子型のエンディングノートについて配布対象年齢や対象者に条件を設けているところもあります。必ず事前に公式サイトや電話で確認してから足をお運びください。 |
2. 市町村がエンディングノートを配布する理由

市町村がエンディングノートを独自に作成して配布するのには、2つの理由があります、
・自治体の負担を減らす
・高齢者に社会で前向きに活躍してもらう
以下の項から、それぞれについて詳しく説明していきましょう。
2-1. 自治体の負担を減らす
エンディングノートを書くことで、生前に不動産の処分や遺品の処分について、親族や行政書士に託すなどの検討をしてもらおうとする狙いがあります。
①空家対策
高齢化の流れを受け、世帯数が急激に減少している地方の自治体では、相続相手がいないために空家となる不動産が増えています。
空家が発生した場合、維持・管理や売却などの手続きをするのは自治体で、その費用も人員も自治体が持っています。
②孤独死対策
故人に身寄りがない場合の葬儀や遺品整理についても同様に、自治体で費用や人員を負担しています。
全国各地の自治体で、こうした負担が毎年増えていき、問題となっているため、エンディングノートの採用が増えてきているのです。
2-2. 元気で前向きなシニアライフのため
これまでの人生で積み上げてきた知識や経験を生かすなど、社会との関わりを持ち続けて心身ともに元気な日々を過ごしてもらいたいという願いが込められています。
多くの人が、エンディングノートを通して「まだまだやりたいことがある」と、新たな目標や挑戦したいことを見つけています。
自治体で作成して無料配布するエンディングノートにも、前向きなシニアが増えるようにとの期待がされているのです。
3. 【形状別】市町村配布のエンディングノートのメリット・デメリット

市町村で作成しているエンディングノートは、冊子とデータファイルがあります。
このうち、データファイルは出力して手書きするものと、キーボードで直接入力のできるものに分かれています。
・冊子型
・PDF形式
・データ入力型
それぞれのメリットとデメリットについてご紹介します。
3-1. 冊子型
窓口などの指定場所で入手できる冊子型のものは、一冊で完結しているので全体を俯瞰しやすいと言えます。
「どこに何が書いてあるか」は、書き手である自分だけでなく、読み手となる家族にとっても大切な事です。遺される家族の負担を少しでも減らしたいという方に向いています。
◼︎メリット
・自治体ならではの地域情報が一緒に掲載されているので、日常生活の中で役に立つことも。
・目次のついているものが多いので、どこに何が書いてあるのかがすぐに分かります。
◼︎デメリット
・項目ごとの書けるスペースが決まっているため、人によってはスペースの多寡が生じてしまいます。
・変更があった場合にも、該当箇所だけの修正はしにくいと言えます。
3-2. PDF形式
市町村の公式ホームページでダウンロードするPDF形式のものは、出力したものに手書きし、自分でファイルなどに綴じます。
変更ページだけ追加で出力して書き直すことができるので、書き損じや修正の跡をそのままにしたくない方におすすめです。
◼︎メリット
・自分の好きな時にダウンロードや出力ができます。
・スペースの足りない項目のページだけ追加することができます。
・変更や更新の際にも、該当するページだけ新たに出力して書き直せばいいので、無駄がありません。
・お気に入りのファイルなどに綴じれば、自分だけの一冊ができます。
◼︎デメリット
・自分で綴じる必要があります。
・増やしたい項目のページを追加したり、ペットを飼っていないなどで不要なページを削除したりした場合は、目次とずれる場合があります。
3-3. データ入力型
市町村の公式ホームページでダウンロードするWord形式のものは、直接キーボードでデータを入力します。
訂正跡が残らず余白が少ないので、仕上がりや見た目の美しさを求める方におすすめです。
◼︎メリット
・書き直しや更新が手軽にできます。
・大切な人へのメッセージなど、推敲してから清書したい項目が書きやすいです。
・項目ごとの大きさを変更することもできるので、余白部分の少ないきれいな仕上がりになります。
◼︎デメリット
・作成をしても出力をしないと、万が一の際にだれも見ることができないものになる可能性があります。
4. 市町村のエンディングノートはこんな人におすすめ

市町村のエンディングノートの内容や形状がわかったところで、どんな方に向いているのかをご説明します。
4-1. エンディングノートの中身を見たことがない方
市販のエンディングノートは、大型の文具店や書店での扱いが中心。なかなか実物を手に取ってみる機会が少ないものです。そしてノートとはいえ、一冊1,000~5,000円が相場。
中身を見るためだけの出費としては、ちょっと高額ですよね。
市町村のエンディングノートなら無料で手に入れることができるものがほとんどなので、「まずは中身を見てみたい」という方に最適です。
4-2. とりあえずどんなものか書いてみたい方
介護や葬儀について、特別なこだわりや強い希望がない場合、最初は書きながら頭と気持ちを整理していくことになります。
市町村のエンディングノートは、市民の声を反映して項目を厳選するなど、シンプルで簡潔な作りのものが多いです。
何が自分に必要なのかを見定めるためにも、「とりあえず」でもまったく問題はないので、書いてみることが大切です。
4-3. たくさんの項目を書ききる自信がない方
市販のエンディングノートを買ってはみたものの、空白部分ばかりが多くなっては残念。しかし項目が多く、考えるべきことが多岐に渡ると、そもそも何から手をつけていいかわからなくなってしまいますよね。
必要最低限の項目を埋めて、その上でやりたいことやメッセージ、エンディングへの希望がさらに湧いてくるのが理想的と言えます。
4-4. 最初からあまりお金をかけたくない方
エンディングノートは、一度書いたらそれで完成というものではありません。
少なくとも年に一度は見直しをして、内容に変更があれば修正を重ねていくものです。
書き慣れてくればご自身にとって重要な項目も見えてくるでしょうから、その時に初めて市販のエンディングノートを見比べてみることをおすすめします。
5. おすすめの市町村エンディングノート5選【全市町村のノート付き】
2020年6月現在、市町村または市町村の社会福祉協議会や地域包括支援センターで入手できるエンディングノートは、全部で37種類あります。
その中から、汎用性とデザイン性が高くておすすめのエンディングノートを5つ選びました。
どれもシンプルながら、必要な書き込み項目は揃っています。
それぞれを詳しくご紹介していますので、使い勝手の良さそうなものやお好みのものをお選びください。
また、この章の最後の項には、すべての市町村エンディングノート一覧を掲載しています。
現在入手できる全国37自治体のリストをすべて網羅しているのは、この記事だけ!どうぞご参考になさってください。
5-1. 埼玉県越谷市|あんしんノート
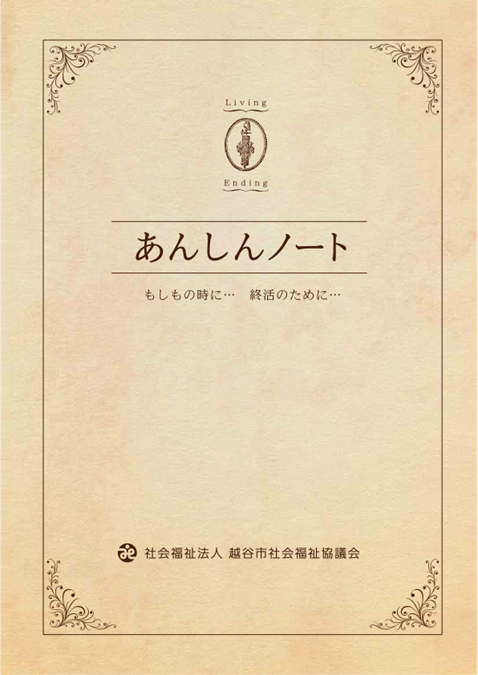
第1章:わたしについて
第2章:介護・医療のことについて
第3章:財産のことについて
第4章:葬儀・お墓のことについて
第5章:個人情報について
大切な人へのメッセージ
経年による色あせを演出したデザイン性の高い表紙です。書き込み項目にも過不足がなく、標準的な内容と言えるでしょう。
第5章の「個人情報について」は、携帯電話の名義人や万が一の際のデータ削除の希望が書き込めます。また、SNSアカウントのIDなどを記載できるため、覚え書きにも使えます。
| 【埼玉県越谷市のエンディングノート】
ノート名:あんしんノート |
5-2. 京都府長岡京市|〜手紙〜大切なあなたへ
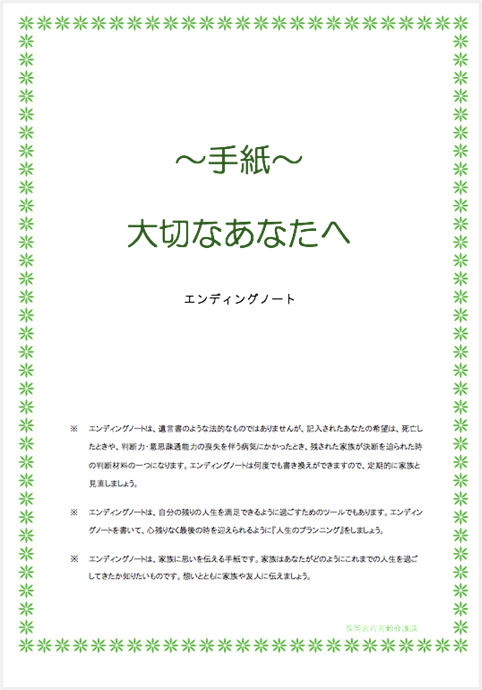
- 表紙
- 親しい人への手紙
- あしあと
- これからの自分へ
- 医療の記録
- もしものとき
- 病気になったとき(介護について)
- 死についての考え方
- 死後の手続き(葬儀)
- 死後の手続き(お墓・ペット)
- 死後の手続き(直後の手続き)
- 死後の手続き(社会保険)
- 死後の手続き(相続・納税)
- メモ・高齢者の相談窓口
5選の中でもっともページ数が多く、項目も多岐にわたります。
「死についての考え方」や「ペットのこと」の項目は、市町村作成のエンディングノートでは珍しい内容です。
Word版があるので、キーボードでの入力もできるのが便利です。
| 【京都府長岡京市のエンディングノート】
ノート名:〜手紙〜大切なあなたへ |
5-3. 横浜市青葉区|わたしノート

第1部〜◯◯ノート〜
・プロフィール
・好きなもの
・大切にしていること
・歩んできた人生
・これからのこと
・わたしの家族・友人などの連絡先
第2部〜もしもノート〜
・財産のこと
・介護のこと
・延命措置のこと
・遺言書のこと
・葬儀・お墓のこと
第3部〜メッセージ〜
3部構成になっていて、第1部は「いまをより良く生きる」ため、自分のこれからのことを書きます。「人生の目標」や「これから取り組みたいこと」など、過去の振り返りだけではなく未来に焦点を当てた、前向きになれるノートです。
第2部は、万が一の際に家族にとってすぐに必要なものをまとめています。
第3部は落ち着いてから読んでもらうもの。頭と気持ちの整理を分けながら書き進めることができる構成と言えます。
| 【神奈川県横浜市青葉区のエンディングノート】
ノート名:わたしノート |
5-4. 福島県田村市|わたしの終活

第1章:わたしのこと
第2章:もしもの時は
第3章:エンディング
第4章:大切な人たち
第5章:財産について
第6章:介護予防について
第7章:認知症について
第8章:相談・手続き
必要な項目が揃った、標準的な内容のエンディングノートです。
葬儀やお墓のことについて、特別な希望がない人にとっては充分なスペースがありますが、連絡先や形見分けについてはあまりスペースが多くないので、必要な分だけページを追加して使うのが良いでしょう。
| 【福島県田村市のエンディングノート】
ノート名:わたしの終活 |
5-5. 埼玉県八潮市|私と家族の安心ノート
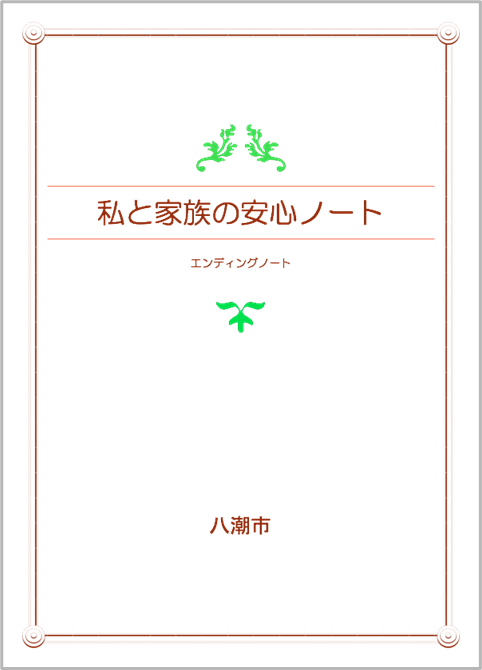
第1章:わたしについて
・私の基本情報
・これまでの私
・私の健康状態
第2章:もしものときは
・重い病気などにかかったら
・認知症などにより、適確な 判断ができなくなったら
・介護が必要になったら
第3章:大切な人たち
・家族/親族
・家族/親族などへのメッセージ
・もしもの時の連絡リスト
・自由記載
ページ数は少ないながら、章立てが簡潔なので頭と心の整理がつけやすいものです。チェック項目式ですいすいと書き進められるので、初めての方にも書きやすい作りと言えます。
地域情報がないので汎用性は高いのですが、住所欄に「埼玉県八潮市」とあらかじめ記載してあるので、気になる方はその部分だけ修正を入れると良いでしょう。
| 【埼玉県八潮市のエンディングノート】
ノート名:私と家族の安心ノート |
5-6. 市町村で入手できるその他のエンディングノート一覧
惜しくも上記5選には入らなかったものの、現在公式HPで配布を行っているその他の市町村のエンディングノートは以下にまとめました。
| 自治体名 | ノート名(公式HPへのリンク) | 自治体名 | ノート名(公式HPへのリンク) |
| 茨城県土浦市 | 私の老後の生き方・暮らし方ノート | 栃木県足利市 | わたしの足あと |
| 栃木県下野市 | しもつけエンディングート | 東京都足立区 | エンディングノート |
| 東京都狛江市 | 狛江市エンディングノート | 東京都府中市 | 未来ノート |
| 神奈川県厚木市 | エンディングノート | 神奈川県茅ヶ崎市 | わたしの覚え書き |
| 神奈川県横浜市南区 | わたしの希望 | 神奈川県横浜市旭区 | 想いをつなぐ |
| 長野県中野市 | しあわせな終活 | 長野県須坂市 | マイ・ノート |
| 滋賀県守山市 | いままでの私これからの私 | 京都府京都市 | わたしの説明書 |
| 大阪府堺市西区 | わたしのメッセージ | 大阪府堺市堺区 | おひとり様の生き方・暮らし方ノート |
| 奈良県橿原市 | わたしのエンディングノート | 奈良県川西町 | 川西町のエンディングノート |
| 島根県江津市 | わたしの未来ノート | 広島県尾道市 | 自分ノート |
| 福岡県宇美町 | おぼえ書き | 熊本県熊本市 | いまを生きる。あなたへ。 |
また、公式HPからのダウンロードはできませんが、窓口で実物を配布している市町村は以下の10箇所です。
配布場所は自治体役所の担当課、地域包括支援センター、ケアプラザなど自治体によって異なります。
現物配布の場合、配布対象者が限定されていることもありますので、事前に各市町村の公式ホームページや電話でご確認のうえ、足をお運びください。
| 【窓口配布のみ行っている市町村一覧】 |
このほか、岐阜県可児市でもエンディングノートの作成が進められています。(2020年6月現在)
エンディングノートを作成する市町村はこれからも増えていくと思われますので、お住まいの市町村が上記リストに掲載されていない場合でも、公式HPや電話などで確認をしてみてください。
6. エンディングノートを書くなら知っておきたい参考記事一覧

初めてエンディングノートを書くとなると、項目に答える形ではあっても、具体的にどんなことを書けばいいのか、悩んでしまう場面もあるでしょう。
エンディングノートについての概要や具体的な書き進め方についての詳細は、以下の記事で詳しくまとめています。ぜひご一読ください。
エンディングノートとは?終活での活用シーンとメリットを詳しく解説
【例文有り】エンディングノートの書き方をわかりやすく解説!
終活でエンディングノートは必要?その役割とデータから分かる重要性
| 『終活の困ったを分かったに』の終活協議会では、一人ではつまづいてしまいがちなエンディングノートの記入について、書き方サポートを行っています。
お一人ひとりに合わせた個別サポートから、10名以上を対象にしたセミナーまで、エンディングノートの書き方について、なんでもご相談をお受けいたします。 ZOOMを使ったビデオ通話によるサポートも対応可能ですので、国内だけでなく海外からも、お気軽にお問い合わせください。 |
7. まとめ
今回は、市町村のエンディングノートについて詳しく解説してきました。
お伝えした基礎知識について振り返ってみましょう。
・独自にエンディングノートを作成し、配布する市町村が増えています。
・市販のエンディングノートよりもページ数は少なめですが、簡潔で必要項目を網羅しています。
・指定の窓口でもらえるほか、公式HPからダウンロードすることによってだれでも無料で入手できるものもあります。
・高齢化に伴う自治体の負担を減らしたり、元気で前向きなシニアライフを送ってもらいたいという目的があります。
また、市町村のエンディングノートを形状で分け、それぞれのメリットとデメリットをお伝えしました。
入手する際は、あらかじめご自身の使用シーンを踏まえてお選びください。
おすすめの市町村エンディングノートを参考に、あなたのお気に入りの一冊が見つかりますように。