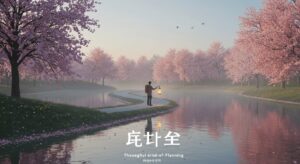「ペットの終活」とは?不安を安心に変えるための愛情準備
「ペットの終活」という言葉を耳にして、胸がざわついたり、漠然とした不安を感じたりしていませんか?初めてこの言葉に触れた方なら、そう感じるのも無理はありません。しかし、ペットの終活は、決して悲しいだけの「お別れの準備」ではないのです。
本当の意味でのペットの終活とは、愛する家族の一員であるペットが、その生涯を最後まで幸せに、そして自分らしく全うできるように、飼い主としてできる限りの準備を整える「愛情のこもった計画」のこと。それは、いつか必ず訪れるお別れの日に、私たちが「できることはすべてやった」と、少しでも穏やかな気持ちでペットを送り出すための、そして深い後悔を避けるための大切なプロセスでもあります。
この活動は、ペットが高齢になったり、病気になったりした時の医療や介護の方針をあらかじめ考えておくこと、飼い主自身に万が一のことがあった場合にペットが路頭に迷わないように預け先を決めておくこと、そして、たくさんの思い出を形に残しておくことなど、非常に多岐にわたります。
この記事では、そんな「ペットの終活」について、何から始めれば良いか分からないというあなたの不安を、具体的な行動に変えるための知識とステップを一つひとつ丁寧に解説していきます。これは、終わりを見据える活動ではなく、最後の瞬間まで愛と責任を全うするための、前向きな取り組みなのです。
ペットの終活はなぜ重要?今から考えるべき3つの理由
ペットが元気なうちは、お別れのことなど考えたくないかもしれません。しかし、冷静に考えられる「今」だからこそ、終活について考えることには大きな意味があります。その理由は、大きく分けて3つあります。
-
後悔を減らし、心穏やかに見送るため:いざという時、動揺して冷静な判断ができないことは少なくありません。「もっとこうしてあげればよかった」という後悔は、深刻なペットロスにつながることも。事前に方針を決めておくことで、その時々の最善の選択ができ、お別れの際の心の負担を軽減できます。
-
ペットのQOL(生活の質)を最後まで守るため:終末期にどのような医療を受けさせたいか、どこで最期を迎えさせてあげたいか。こうした希望を明確にしておくことは、ペットが最後まで尊厳を保ち、穏やかに過ごすために不可欠です。
-
飼い主自身の「もしも」に備えるため:飼い主の突然の病気や事故、高齢化など、ペットの世話を続けられなくなる可能性は誰にでもあります。終活は、そうした不測の事態が起きても、愛するペットが安心して暮らし続けられる環境を確保するためのセーフティーネットなのです。
終活は「お別れの準備」ではなく「最後まで幸せにする」ための計画
「終活」という言葉には、どうしてもネガティブな響きが伴いがちです。しかし、ペットの終活の本質は、死を待つことではありません。それは、「限りある時間の中で、どうすればこの子が一番幸せでいられるか」を考え、実行していくためのポジティブな計画です。
例えば、ペットがシニア期に入ったら、若い頃とは違う楽しみ方を見つけるのも立派な終活です。激しい運動ができなくなっても、日当たりの良い場所で一緒にひなたぼっこをしたり、優しくマッサージをしてあげたり。日々の暮らしの中で、ペットの心と体の変化に寄り添い、愛情を注ぐこと。それこそが、終活の最も大切な部分と言えるでしょう。
「ペットの終活は、お別れの日のためだけにあるのではありません。それは、今日という一日を、そして明日という一日を、ペットと飼い主さんが共に最高に幸せなものにするためのロードマップなのです。」(ペットケア専門家)
お別れはいつか必ずやってきます。その事実から目を背けるのではなく、真正面から向き合い、今できる愛情の形を考えること。それが、ペットの終活が私たちに教えてくれる、最も尊い価値観なのかもしれません。
ペットの終活はいつから始めるべき?最適なタイミングの見極め方

「ペットの終活、いつから始めたらいいの?」これは、多くの飼い主さんが抱く共通の疑問です。結論から言えば、「早すぎる」ということはありません。むしろ、飼い主もペットも心身ともに元気で、冷静な判断ができるうちに始めるのが理想的です。
とはいえ、具体的なきっかけが欲しいと感じる方も多いでしょう。一般的に、ペットの終活を意識し始めるタイミングとしては、以下のような時期が挙げられます。
-
ペットがシニア期に入った時:犬や猫の場合、一般的に7〜8歳頃からシニア期(高齢期)とされます。体の変化が見られ始めるこの時期は、将来の介護や医療について考え始める良いきっかけになります。
-
飼い主自身が一定の年齢になった時:ご自身の年齢が50代、60代になった時など、将来のライフプランを考えるタイミングで、ペットの将来についても一緒に計画を立てる方が増えています。
-
ペットや飼い主に病気が見つかった時:病気は、否応なく「もしも」を意識させます。診断をきっかけに、今後の治療方針や万が一の備えについて、具体的に考え始める必要があります。
-
ライフステージの変化があった時:転勤、結婚、出産など、生活環境が大きく変わるタイミングも、ペットの将来について改めて考える良い機会です。
大切なのは、「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにしないこと。問題が起きてから慌てて準備するのと、余裕を持って備えておくのとでは、心身の負担が全く違います。思い立ったが吉日。この記事を読んでいる「今」が、あなたにとっての最適なタイミングなのかもしれません。
【ペットのために】今からできる終活リスト7選

ここからは、具体的に「ペットのために」何ができるのか、7つの項目に分けて詳しく見ていきましょう。どれも、愛するペットが最後まで安心して暮らすために重要なことばかりです。できることから一つずつ、リストをチェックするような気持ちで取り組んでみてください。
1. 思い出をたくさん作る・形に残す
終活の第一歩として、最も楽しく、そして最も大切なのが「思い出作り」です。これは、来るべきペットロスを乗り越えるための心の支えにもなります。ペットが元気なうちに、たくさんの愛情を注ぎ、その証を形に残しておきましょう。
特別な旅行やイベントも素敵ですが、何気ない日常こそが宝物です。一緒に昼寝をする姿、おやつをねだる表情、楽しそうに遊ぶ様子など、日々の愛しい瞬間を写真や動画でたくさん記録してください。最近では、ペットの毛や爪、足形などを保存できるメモリアルグッズも人気です。こうした形に残る思い出は、お別れの後にあなたの心を温め、慰めてくれる存在になるはずです。
2. 医療・介護の方針を決めておく
ペットが高齢になったり、大きな病気を患ったりした時、どのような医療や介護を受けさせたいか、事前に家族と話し合い、方針を決めておくことは非常に重要です。いざという時に、冷静な判断を下すための道しるべとなります。
考えるべきポイントは多岐にわたります。例えば、「延命治療はどこまで望むか」「痛みを和らげる緩和ケアを重視するか」「介護が必要になった場合、在宅でみるか、施設に預けるか」などです。これらの問いに絶対的な正解はありません。ペットの性格やこれまでの生き方、そして家族の価値観や生活状況を総合的に考慮し、「この子にとっての最善は何か」を考えていくプロセスが大切です。
在宅での看取りと安楽死の選択肢について
終末期の過ごし方として、住み慣れた自宅で最期を迎えさせてあげる「在宅での看取り」を希望する飼い主さんは少なくありません。一方で、ペットが回復の見込みのない病気で、激しい苦痛に苛まれている場合、「安楽死」もまた、苦しみから解放してあげるための最後の愛情ある選択肢となり得ます。
これは非常に重く、辛い決断です。だからこそ、元気なうちから「もしも、その時が来たら」と想定し、かかりつけの獣医師と相談しておくことが重要です。ペットのQOL(生活の質)をどう評価するか、どのような状態になったら安楽死を検討するのか。事前に話し合っておくことで、土壇場での苦悩を少しでも和らげることができます。
かかりつけ医との情報共有と緊急連絡先の整理
医療・介護方針を考える上で、かかりつけの獣医師との連携は不可欠です。日頃からペットの健康状態についてよく相談し、信頼関係を築いておきましょう。そして、いざという時に慌てないよう、必要な情報を一箇所にまとめておくことが大切です。
具体的には、以下の情報を整理し、家族と共有しておきましょう。
-
かかりつけ動物病院の連絡先(診察時間、休診日も)
-
夜間や休日に対応してくれる救急動物病院の連絡先
-
これまでの病歴、アレルギー、服用中の薬などの医療情報
-
ペット保険に加入している場合は、その証券番号と連絡先
これらの情報を「ペットのエンディングノート」などにまとめておくと、万が一の際に誰が見ても状況を把握でき、迅速な対応につながります。
3. 医療費の準備(貯蓄やペット保険の見直し)
ペットの高齢化に伴い、医療費は増加する傾向にあります。特に、慢性疾患の治療や高度な医療、長期的な介護が必要になった場合、その費用は決して少なくありません。経済的な理由で必要な治療を諦めるという辛い選択をしないためにも、計画的な準備が不可欠です。
具体的な準備方法としては、まず「ペット用の貯蓄」を始めることが挙げられます。毎月決まった額を積み立てるなど、無理のない範囲で計画を立てましょう。もう一つの有効な手段が「ペット保険」です。すでに加入している場合でも、シニア期になると補償内容が変わったり、更新に制限が出たりすることがあります。ペットの年齢や健康状態に合わせて、プランが適切かどうか定期的に見直すことが重要です。まだ加入していない場合は、シニアペットでも入れる保険を検討してみるのも良いでしょう。
4. 葬儀・供養の方法を検討する
愛するペットとのお別れのセレモニーは、飼い主の心を整理し、ペットロスを乗り越えるための大切な儀式です。悲しみの渦中にいる中で慌てて業者を探すのは大変なこと。事前にどのような形で見送りたいかを考え、情報を集めておきましょう。
ペットの葬儀には、主に以下のような選択肢があります。
-
個別火葬:ペット一体ずつ個別に火葬し、お骨を返してもらう方法。
-
合同火葬:他のペットたちと一緒に火葬する方法。費用は抑えられますが、お骨は返ってきません。
-
訪問火葬:火葬炉を搭載した車が自宅まで来て、その場で火葬してくれるサービス。
火葬後の供養方法も、自宅で手元供養する、ペット霊園に納骨・埋葬する、自然に還す散骨など様々です。それぞれのメリット・デメリット、費用などを比較検討し、自分たちの気持ちに合った方法を選びましょう。事前にいくつかの業者に問い合わせ、対応や料金体系を確認しておくと安心です。
5. 犬・猫・小動物など種類別の注意点
ペットの終活は、その動物の種類や特性によって注意すべき点が異なります。ここでは代表的なペットについて、特有のポイントを解説します。
【犬の場合】
犬は犬種によって体格や寿命、かかりやすい病気が大きく異なります。大型犬は関節系の疾患や寝たきりになるリスクが高いため、介護しやすい環境づくり(滑りにくい床材、スロープの設置など)が重要になります。また、認知症のような症状が見られることもあり、夜鳴きや徘徊への対策も考えておく必要があります。かかりつけ医と相談し、犬種特有のシニア期の病気について知識を得ておきましょう。
【猫の場合】
猫は腎臓病や甲状腺機能亢進症など、高齢期に特有の病気にかかりやすいことで知られています。病気の兆候を見逃さないよう、定期的な健康診断がより一層重要になります。また、猫は体調不良を隠す習性があるため、食欲や飲水量、トイレの様子など、日々の細かな変化に気を配ることが大切です。高い場所に登れなくなるなど、身体能力の低下に合わせて、段差の少ない落ち着ける寝床を用意してあげるなどの配慮も必要です。
【うさぎ・ハムスターなどの小動物の場合】
うさぎやハムスター、小鳥などの小動物は、犬猫に比べて寿命が短いことが多く、終活をより早期から意識する必要があります。彼らの最大の課題は、専門的に診てくれる動物病院が限られることです。元気なうちから、エキゾチックアニマルを診療できる病院を見つけておくことが、終活の最重要項目と言えるでしょう。また、体が小さいため、体調の急変が命取りになることも少なくありません。日々の観察を怠らず、少しでも異変を感じたらすぐに病院へ連れて行ける体制を整えておきましょう。
【飼い主のために】万が一に備える終活リスト5選

ペットの終活は、ペット自身のためだけではありません。飼い主さん自身の「もしも」に備え、残されるペットの未来を守ることも、同じように重要です。ここでは、飼い主さんのために準備しておくべき5つの項目を解説します。
1. ペットの預け先・引き取り手を探しておく
飼い主さんが病気や事故で入院したり、亡くなってしまったりした場合、ペットは誰がお世話をしてくれるのでしょうか。この問題は、ペットの終活において最も重要かつ切実な課題です。元気なうちに、責任を持ってペットの将来を託せる人や場所を確保しておく必要があります。
第一の選択肢は、家族や親戚、信頼できる友人です。しかし、安易にお願いするのは禁物です。ペットを飼うには、愛情だけでなく、時間的、経済的、体力的な負担が伴います。引き受けてくれる可能性がある人とは、事前に「もし私に何かあったら、この子をお願いできないか」と真剣に話し合い、相手の意思を明確に確認しておくことが不可欠です。その際は、お世話にかかる費用をどうするかまで具体的に決めておくと、後のトラブルを防げます。
身近に頼れる人がいない場合は、動物保護団体やNPO法人、有料の老犬・老猫ホーム(終生飼養施設)なども選択肢となります。これらの施設は、それぞれ受け入れ条件や費用が異なります。事前に情報を集め、見学に行くなどして、信頼できる施設かどうかを自分の目で確かめておくことが大切です。
2. 飼い主にもしものことがあった際の法的・金銭的準備
ペットの預け先が決まったとしても、そのお世話には当然お金がかかります。新しい飼い主さんに経済的な負担をかけずに、ペットがこれまで通りの生活水準を維持できるようにするためには、法的な裏付けのある金銭的準備が非常に有効です。
日本の法律では、残念ながらペットは「物」として扱われるため、直接財産を相続させることができません。しかし、飼い主さんの財産を「ペットのお世話のために使ってもらう」仕組みを作ることは可能です。これにより、飼い主さんの意思が確実に実行され、大切なペットの生涯を守ることができます。
主な方法としては、「遺言」「負担付死因贈与契約」「ペット信託」などがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、手続きの複雑さや費用も異なります。次のセクションで詳しく比較しますが、これらの方法は専門的な知識を要するため、安易に自己判断せず、専門家のアドバイスを仰ぐことが賢明です。
主な法的準備の比較表(ペット信託・遺言など)
ペットに財産を確実に残すための主な法的準備について、それぞれの特徴を比較してみましょう。ご自身の状況や希望に最も合った方法を見つけるための参考にしてください。
|
方法 |
概要 |
メリット |
デメリット |
費用目安 |
|---|---|---|---|---|
|
遺言 |
遺言書で、ペットの世話をすることを条件に、特定の人(新しい飼い主)に財産を遺す(負担付遺贈)。 |
・比較的簡単に作成できる。 |
・受遺者が負担(ペットの世話)を履行しないリスクがある。 |
数万円~(専門家に依頼する場合) |
|
負担付死因贈与契約 |
飼い主の死亡によって効力が発生する贈与契約。ペットの世話を負担として、新しい飼い主と生前に契約を結ぶ。 |
・生前に双方の合意で契約するため、確実性が高い。 |
・契約相手(新しい飼い主)を見つける必要がある。 |
10万円~(専門家に依頼する場合) |
|
ペット信託® |
信頼できる人や法人(受託者)に財産を託し、飼い主の死亡後、その財産からペットの飼育費を新しい飼い主(受益者)に支払ってもらう仕組み。 |
・飼い主の意思が最も確実に反映される。 |
・仕組みが複雑。 |
30万円~(初期費用。別途管理費等がかかる場合も) |
※費用はあくまで一般的な目安であり、依頼する専門家や信託する財産の額によって変動します。
専門家(弁護士・行政書士)への相談も検討しよう
前述の比較表を見てわかる通り、ペットのために法的な準備をするには、専門的な知識が不可欠です。特に「負担付死因贈与契約」や「ペット信託」は、契約書の作成が極めて重要であり、内容に不備があると、いざという時に飼い主の意思が実現されない可能性があります。
このような事態を避けるためにも、弁護士や行政書士といった法律の専門家に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法的なトラブル全般に対応でき、代理人として交渉も可能です。一方、行政書士は、契約書や遺言書の作成といった書類作成のプロフェッショナルです。
最近では、ペットの法務に詳しい専門家も増えています。初回の相談は無料で行っている事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。専門家の助けを借りることは、あなたの「ペットを守りたい」という想いを、確実な形にするための最も賢明な投資です。
3. 家族との話し合い方と合意形成のポイント
ペットの終活は、飼い主さん一人だけで進められるものではありません。同居している家族はもちろん、離れて暮らす親族とも、事前に情報を共有し、理解と協力を得ておくことが非常に重要です。特に、将来ペットのお世話をお願いする可能性がある人とは、丁寧な合意形成が不可欠です。
話し合いを切り出す際は、重苦しい雰囲気にならないよう配慮しましょう。「この子がこれからもずっと幸せに暮らせるように、元気なうちにみんなで考えておきたいんだ」と、ペットへの愛情を前面に出して、前向きなテーマとして提案するのがポイントです。その上で、終末期医療の方針や、飼い主に万が一のことがあった場合の対応について、具体的に話し合います。
意見が食い違うこともあるかもしれません。例えば、医療費のかけ方や安楽死の判断など、価値観が問われる問題では、すぐに結論が出ないこともあります。大切なのは、感情的にならず、お互いの意見を尊重し、粘り強く対話を続けること。「ペットにとっての最善は何か」という共通のゴールを常に意識すれば、きっと合意点が見つかるはずです。
4. 自身のエンディングノートにもペットの情報を記載する
もしあなたがご自身の「エンディングノート」を作成しているのであれば、そこにペットに関する情報を必ず記載しておきましょう。これは、残された家族や関係者が、あなたの意思を尊重し、スムーズにペットの世話を引き継ぐための重要な情報源となります。
記載すべき主な項目は以下の通りです。
-
ペットの基本情報:名前、種類、生年月日、マイクロチップ番号など。
-
ペットの引き取り手について:誰にお願いしてあるか、その人の連絡先。
-
ペットのための財産について:ペット信託や遺言など、どのような準備をしているか。関連書類の保管場所も明記します。
-
ペット自身のエンディングノートの保管場所:ペットの詳細な情報を記したノートがどこにあるかを伝えます。
-
かかりつけの動物病院:病院名と連絡先。
-
あなたからペットへの最後のメッセージ:これは法的な意味合いはありませんが、あなたの愛情を伝える大切な記録です。
これらの情報を書き記しておくことで、万が一の時、残された人々はあなたの想いを汲み取り、迷うことなくペットの未来を守るための行動を起こすことができるのです。
後悔しないための「ペットのエンディングノート」の作り方と活用法

ペットの終活を進める上で、非常に役立つツールが「ペットのエンディングノート」です。これは、ペットに関するあらゆる情報を一冊にまとめたもので、いわば「ペットの取扱説明書」。飼い主さん自身に何かあった時、新しい飼い主さんが困らないように、そして、日々の健康管理や緊急時の備えとしても活用できます。
市販のノートや自治体が配布しているものもありますが、もちろん普通のノートに自分で項目を立てて作成しても構いません。大切なのは、必要な情報が網羅されていることです。このノートがあるだけで、いざという時の安心感が大きく変わります。作成すること自体が、ペットとの向き合い方を見つめ直す良い機会にもなるでしょう。今日からでも始められる、具体的で愛情のこもった終活の第一歩です。
【記入例付き】エンディングノートに書くべき必須項目
ペットのエンディングノートに決まった形式はありませんが、以下の項目は必ず盛り込んでおきましょう。具体的で詳細な情報ほど、いざという時に役立ちます。
-
プロフィール:名前、種類、性別、生年月日、マイクロチップ番号、ペット保険の情報など。
-
出会いの記録:どこで出会ったか、家族になった日のことなど、思い出を綴ります。
-
性格・好きなこと・嫌いなこと:
[記入例] 人懐っこいが、大きな音と掃除機が苦手。お腹を撫でられるのが大好きで、お気に入りのオモチャは青いボール。
-
健康の記録:
[記入例] かかりつけ医:〇〇動物病院(電話番号)。アレルギー:鶏肉。持病:慢性腎臓病(3ヶ月に1回通院)。服用中の薬:〇〇を1日2回。
-
食事の記録:普段食べているフードの種類、量、回数、おやつの種類や注意点。
-
1日の過ごし方:散歩の時間やルート、トイレの習慣、寝る場所など。
-
緊急連絡先:飼い主にもしものことがあった際の、ペットの引き取り手の連絡先、かかりつけ医、夜間救急病院など。
-
最期に寄せて:延命治療や看取りに関する希望、葬儀・供養の方法についての希望。
-
飼い主からのメッセージ:ペットへの感謝の気持ちや愛情を自由に書き記します。
エンディングノートを保管・共有する方法
エンディングノートは、作成するだけでは意味がありません。いざという時に、必要な人の目に触れる場所になければ、その役割を果たせないのです。
まず、保管場所を決めましょう。自宅の本棚や引き出しなど、家族が分かりやすい場所に保管するのが基本です。防災リュックの中にコピーを一部入れておくのも良いでしょう。そして最も重要なのが、ノートの存在と保管場所を、ペットの引き取り手や同居の家族に必ず伝えておくことです。
また、原本は手元に置きつつ、コピーを信頼できる人に預けておいたり、スマートフォンで撮影したりスキャンしたりして、デジタルデータとしてクラウド上(GoogleドライブやDropboxなど)に保存しておくのも賢明な方法です。これにより、災害時などに原本が紛失しても、情報が失われるのを防ぐことができます。定期的に内容を見直し、最新の情報に更新することも忘れないようにしましょう。
知っておきたい「ペットロス」のこと|心の準備と乗り越え方
どれだけ万全の準備をしても、愛するペットを失った悲しみは計り知れません。この深い悲しみや喪失感は「ペットロス」と呼ばれ、時に心身に深刻な影響を及ぼすこともあります。ペットの終活を考えることは、このペットロスと向き合うための心の準備をすることでもあります。
実は、終活に真剣に取り組むこと自体が、ペットロスを和らげる効果があると言われています。「やるべきことはすべてやった」「最後までこの子のために最善を尽くせた」という感覚は、お別れの後の深い後悔を軽減し、自分を責める気持ちを和らげてくれます。思い出をたくさん形に残しておくことも、悲しみを乗り越える過程で大きな支えとなるでしょう。
それでも、悲しみの波は必ず訪れます。そんな時は、無理に気丈に振る舞う必要はありません。泣きたい時は思い切り泣き、信頼できる友人や家族に気持ちを話しましょう。「たかがペット」と言う人もいるかもしれませんが、あなたにとってかけがえのない家族を失ったのですから、悲しむのは当然のことです。ペットロス専門のカウンセリングや、同じ経験をした人々が集う自助グループなども存在します。一人で抱え込まず、外部の助けを求めることも大切です。時間をかけて、ゆっくりと、ペットとの美しい思い出を力に変えていきましょう。
まとめ:愛するペットのために、今日から始める第一歩
ここまで、「ペットの終活」について、その意味から具体的な準備リストまでを詳しく解説してきました。情報量が多く、少し圧倒されてしまったかもしれません。しかし、すべてを一度にやろうとする必要はありません。
ペットの終活とは、お別れを悲しむための活動ではなく、「愛する家族が最後の瞬間まで幸せであるように」と願う、究極の愛情表現です。それは、ペットのQOLを守り、飼い主自身の後悔を減らし、万が一の事態にも備える、責任ある飼い主としての最後の務めでもあります。
もし、あなたが「何から始めようか」と迷っているなら、まずは「ペットのエンディングノート」を1ページ書いてみることから始めてはいかがでしょうか。ペットの名前や好きな食べ物を書き出すだけでも、それは立派な終活の第一歩です。その小さな一歩が、あなたと愛するペットの未来を守る、大きな安心へと繋がっていきます。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、愛するペットのために今日から行動を起こすきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。
-
ペットの終活とは:単なる「お別れの準備」ではなく、愛するペットが最期まで幸せに、自分らしく過ごせるように計画し、飼い主自身の後悔を減らすための「愛情準備」です。
-
なぜ重要か:突然の別れや飼い主の万が一の事態に備え、ペットの医療・介護方針を冷静に判断し、経済的な負担やペットロスの深刻化を防ぐために不可欠です。
-
具体的な準備:準備は「ペットのため」と「飼い主のため」の2つの側面があります。医療方針の決定や葬儀の検討から、飼い主にもしものことがあった際の預け先確保や法的準備まで、網羅的な計画が求められます。
-
今日からできること:まずはペットの情報をまとめる「エンディングノート」の作成から始めるのがおすすめです。ペットの個性や健康状態を記録し、家族と共有することが、終活の第一歩となります。