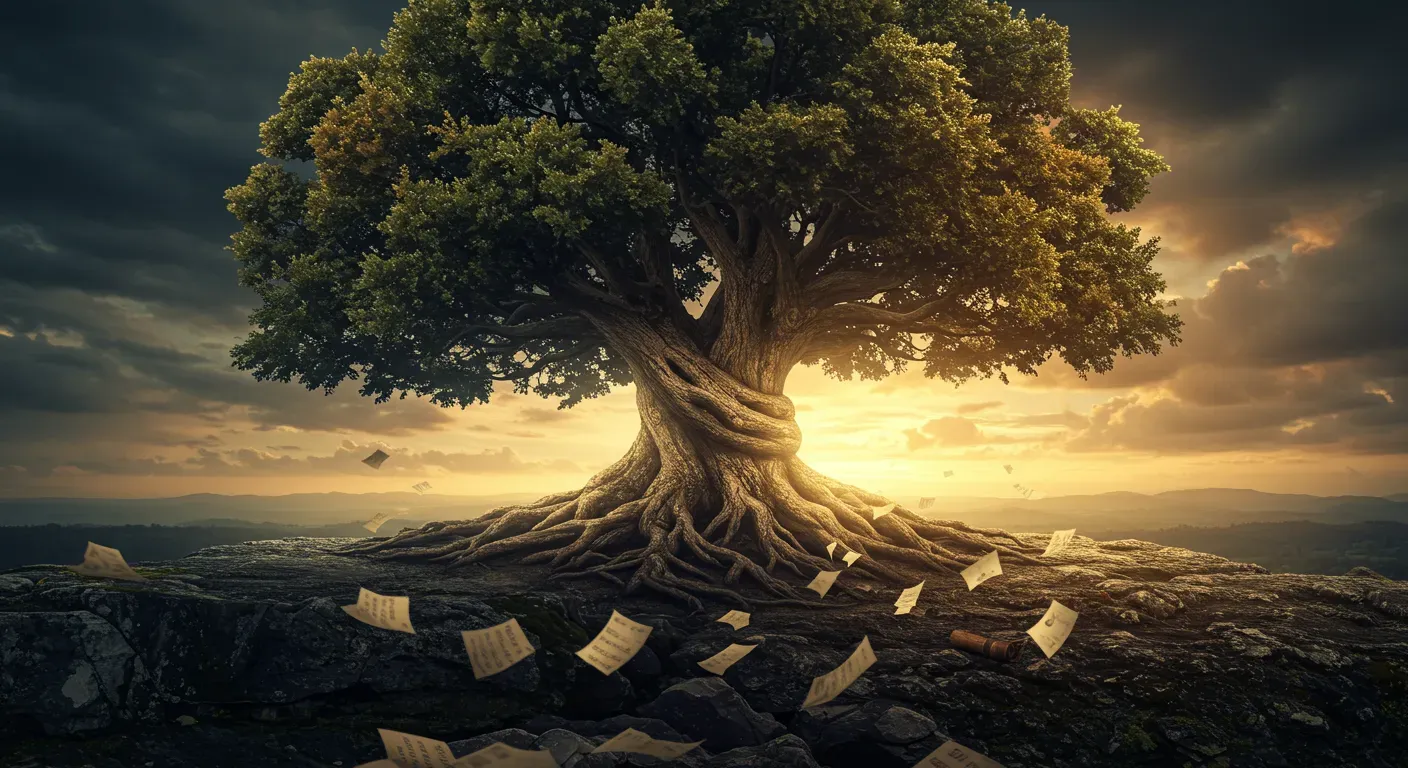Table of Contents
- 相続は「争続」に?他人事ではない遺産トラブルの現実
- 相続でもめる割合は?遺産額5,000万円以下が最も多いという事実
- 相続でもめる家族の10の特徴と主な原因
- 1. 遺産の分けにくさ|不動産や非上場株式など
- 【事例】自宅不動産しかなく、売却か同居かで意見が対立
- 2. 相続人間の関係性|兄弟仲の悪さや疎遠
- 3. 被相続人の生前の言動|介護負担や生前贈与の不公平感
- 「長男の嫁」など法定相続人でない人の貢献
- 4. 遺言書の問題|不公平な内容や形式の不備
- 5. 複雑な家族関係|再婚相手の連れ子、内縁の妻、認知した子など
- 家族の絆を守るために。相続トラブルを未然に防ぐ5つの予防策
- 1. 法的に有効な遺言書を作成する(公正証書遺言がおすすめ)
- 2. 生前贈与を計画的に行い、記録を残す
- 3. 生命保険を活用して「代償分割」の資金を準備する
- 4. 家族信託を検討し、財産の管理と承継をスムーズにする
- 5. 【新たな選択肢】中立な第三者(相続手続き代行サービス)に依頼する
- 感情的な対立を避け、円満な話し合いを促進
- 多忙・遠方の相続人の負担を軽減し、手続きミスを防ぐ
- もし相続でもめてしまったら?冷静に進めるべき3つの対処法
- ステップ1:当事者間での「遺産分割協議」
- ステップ2:家庭裁判所での「遺産分割調停」
- ステップ3:最終手段としての「遺産分割審判・訴訟」
- 相続トラブルは誰に相談すべき?専門家の役割と費用目安
- 弁護士:法的な代理交渉や手続き全般を依頼
- 司法書士:不動産の名義変更(相続登記)を依頼
- 税理士:相続税の申告を依頼
- 【費用を具体的に把握】相続手続き代行の料金プラン比較
- 主要な手続きの費用相場比較表
- まとめ:円満な相続は事前の準備から
- 相続のもめる問題に関するよくあるご質問(FAQ)
-
相続トラブルの約75%は遺産額5,000万円以下の家庭で発生しており、誰にでも起こりうる身近な問題です。
-
主な原因は「分けにくい不動産」「相続人間の関係性」「生前の不公平感」「遺言書の問題」「複雑な家族関係」に集約されます。
-
有効な予防策として、法的に不備のない「公正証書遺言」の作成、計画的な「生前贈与」、生命保険や家族信託の活用が挙げられます。
-
万が一もめてしまった場合は、当事者間の協議から始め、まとまらなければ家庭裁判所の調停、最終的には審判へと進みます。
-
トラブル予防や解決には、弁護士・司法書士・税理士といった専門家や、中立な立場で手続きを支援する「相続手続き代行サービス」への早期相談が鍵となります。
相続は「争続」に?他人事ではない遺産トラブルの現実
「うちには大した財産はないから大丈夫」「兄弟仲は良いから、もめるはずがない」。多くの方がそう考えているかもしれません。しかし、相続がきっかけで家族の絆にひびが入り、骨肉の争いに発展してしまうケースは、決してテレビドラマの中だけの話ではありません。相続が「争続」という言葉で語られるように、財産の多少にかかわらず、どんな家庭にも起こりうる非常に身近な問題なのです。
特に、親が高齢になり「もしもの時」を考え始めたとき、漠然とした不安を感じる方は少なくないでしょう。このままで、本当に家族は円満に相続を終えられるだろうか。この記事では、そんな不安を抱えるあなたが、家族の絆を守りながら円満な相続を迎えるために、知っておくべきトラブルの現実と、今からできる具体的な準備について、分かりやすく解説していきます。
相続でもめる割合は?遺産額5,000万円以下が最も多いという事実
「相続でもめるのは、お金持ちの家の話」というイメージは、実は大きな誤解です。令和3年度の司法統計によると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち、実に約75%が遺産総額5,000万円以下のケースで占められています。さらに、その中でも最も多いのが「1,000万円超5,000万円以下」の層で、全体の約43%にものぼります。
このデータが示すのは、一般的な家庭でごく普通に起こりうる「自宅不動産+預貯金」といった相続こそが、最もトラブルになりやすいという厳しい現実です。遺産額が少ないからこそ、「自分はこれだけもらえるはず」という期待と現実のギャップが生まれやすく、また、分けにくい不動産が主な財産である場合、分割方法をめぐって意見が対立しやすくなるのです。
相続トラブルは、資産の額ではなく、家族関係や準備の有無によって引き起こされる問題です。まずは「我が家も例外ではない」という認識を持つことが、円満な相続への第一歩となります。
相続でもめる家族の10の特徴と主な原因
では、具体的にどのような家族が相続でもめやすいのでしょうか。長年の相続トラブルの事例を分析すると、いくつかの共通した特徴や原因が見えてきます。ここでは、特に注意すべき代表的な5つの原因を、具体的なケースを交えながら掘り下げていきます。ご自身の家族に当てはまる点がないか、少し立ち止まって考えてみてください。これらの原因を事前に理解しておくことが、トラブルを未然に防ぐための重要なヒントになります。
1. 遺産の分けにくさ|不動産や非上場株式など
相続でもめる最大の原因の一つが、遺産の「分けにくさ」です。預貯金のように金額が明確で均等に分けられる財産と違い、不動産や自社株(非上場株式)は物理的に分割することが困難です。例えば、相続人が3人いるのに、遺産が実家の土地と建物だけだった場合、どうやって公平に分ければよいでしょうか。
誰か一人が相続するなら他の相続人にお金を支払う(代償分割)必要がありますが、その資金がなければ家を売却して現金化(換価分割)するしかありません。しかし、「親との思い出が詰まった家を売りたくない」と考える相続人がいれば、そこから深刻な対立が始まってしまいます。このように、遺産の大部分が分けにくい資産で構成されている場合、トラブルのリスクは格段に高まるのです。
【事例】自宅不動産しかなく、売却か同居かで意見が対立
父が亡くなり、相続人は長男と次男の2人。遺産は時価3,000万円の実家のみ。長男は「親の家は自分が引き継ぎ、家族と住みたい」と主張。一方、遠方で家庭を持つ次男は「法定相続分である1,500万円を現金で欲しい。家を売却してほしい」と要求。長男に代償金を支払う余裕はなく、話し合いは完全に平行線をたどり、兄弟関係は急速に悪化してしまいました。
2. 相続人間の関係性|兄弟仲の悪さや疎遠
相続は、それまでの家族関係が如実に表れる鏡のようなものです。もともと兄弟仲が悪かったり、長年にわたって疎遠だったりすると、相続を機に積年の不満や嫉妬が一気に噴出することがあります。「昔から親は兄ばかり可愛がっていた」「弟はいつも自分勝手だった」といった過去の感情が、遺産分割の話し合いに影を落とし、冷静な議論を妨げます。
また、相続人の配偶者が話し合いに口を出すことで、問題がさらに複雑化するケースも少なくありません。当事者同士であればまとまる話も、それぞれの家族の利害が絡むことで、収拾がつかなくなってしまうのです。相続は単なる財産の分配ではなく、家族の歴史と感情の清算でもあるのです。
3. 被相続人の生前の言動|介護負担や生前贈与の不公平感
被相続人(亡くなった方)の生前の言動も、トラブルの大きな火種となります。特に問題となりやすいのが、「介護の負担」と「生前贈与」の不公平感です。
例えば、長年にわたり親の介護を一身に引き受けてきた相続人が「自分はこれだけ貢献したのだから、遺産を多くもらう権利がある(寄与分)」と主張するのに対し、他の相続人が「親の面倒を見るのは当たり前だ」と認めないケース。また、特定の子供だけが住宅購入資金や学費の援助(特別受益)を受けていたことが発覚し、「自分は何もしてもらっていないのに不公平だ」と他の相続人が不満を抱くケースです。こうした生前の貢献や援助は、法律上の権利として認められにくい場合も多く、感情的なしこりを残しやすい問題です。
「長男の嫁」など法定相続人でない人の貢献
特に見過ごされがちなのが、「長男の嫁」のように法定相続人ではない親族による介護の貢献です。法律上、相続権のない人は、どれだけ献身的に介護をしても、原則として遺産を受け取ることはできません(特別寄与料という制度はありますが、請求のハードルは高いです)。夫である長男がその貢献に報いようとしても、他の兄弟が反対すれば、長年の苦労が全く報われないという理不尽な状況が生まれ、深刻な家族間の亀裂につながることがあります。
4. 遺言書の問題|不公平な内容や形式の不備
「遺言書さえあれば安心」と考えるのは早計です。遺言書が原因で、かえってトラブルが深刻化するケースも少なくありません。例えば、「全財産を長男に相続させる」といった極端に不公平な内容の遺言書は、他の相続人の「遺留分(法律で保障された最低限の相続分)」を侵害している可能性が高く、遺留分侵害額請求という新たな争いを引き起こします。
また、自筆証書遺言の場合、日付や署名、押印がないといった形式的な不備で無効になってしまうこともあります。せっかく書いた遺言が無効になれば、結局は相続人全員での遺産分割協議が必要となり、故人の想いを実現できなくなってしまいます。遺言書は、内容の公平性と法的な有効性の両方を満たしてこそ、真の力を発揮するのです。
5. 複雑な家族関係|再婚相手の連れ子、内縁の妻、認知した子など
現代の家族構成の多様化も、相続を複雑にする一因です。例えば、被相続人に再婚経験があり、前妻との間に子がいる場合や、後妻に連れ子がいる場合、誰がどのくらいの割合で相続するのか、関係者全員の合意形成は非常に難しくなります。お互いに面識がなかったり、感情的なわだかまりがあったりすれば、話し合いは困難を極めるでしょう。
また、長年連れ添った内縁の妻には、法律上の相続権がありません。被相続人が内縁の妻に財産を残したいと考えていた場合、遺言書がなければその想いは叶えられません。さらに、亡くなった後に婚外子が「認知してほしい」と現れるケースもあり、相続関係が根底から覆ることもあります。こうした複雑な関係性が存在する場合、専門家を交えずに円満解決を目指すのは極めて困難です。
家族の絆を守るために。相続トラブルを未然に防ぐ5つの予防策
ここまで相続でもめる原因を見てきましたが、不安になる必要はありません。これらのトラブルの多くは、事前の準備によって防ぐことが可能です。「もしもの時」に備えて、元気なうちから対策を講じておくことこそが、家族への最大の思いやりと言えるでしょう。ここでは、家族の絆を守り、円満な相続を実現するための具体的な5つの予防策をご紹介します。何から手をつければ良いか分からないという方も、まずは自分たちに合った方法を見つけることから始めてみてください。
1. 法的に有効な遺言書を作成する(公正証書遺言がおすすめ)
相続トラブルを防ぐ最も確実で基本的な方法は、法的に有効な遺言書を作成することです。遺言書があれば、原則としてその内容通りに遺産が分割されるため、相続人間での無用な争いを避けることができます。
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、専門家が強く推奨するのは「公正証書遺言」です。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式の不備で無効になったり、紛失や改ざんのリスクがあったり、死後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になったりと、デメリットも少なくありません。
一方、公正証書遺言は、公証人が内容を確認し、法律の専門家として作成するため、形式不備で無効になる心配がほぼありません。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクもなく、検認手続きも不要です。作成には費用と手間がかかりますが、残された家族の負担を考えれば、その価値は計り知れません。「なぜこの分け方にしたのか」という想いを付言事項として書き添えておくことも、家族の納得感を得るために非常に有効です。
2. 生前贈与を計画的に行い、記録を残す
生前に財産を少しずつ次の世代へ移転させていく「生前贈与」も、有効な相続対策の一つです。相続財産そのものを減らすことで、将来の遺産分割の対象を少なくし、争いの種を減らすことができます。年間110万円までの基礎控除を利用した暦年贈与や、相続時精算課税制度、住宅取得資金贈与の特例など、様々な制度があります。
ただし、生前贈与を行う上で最も重要なのは、「誰に、いつ、いくら贈与したか」を明確に記録しておくことです。口約束や曖昧な形での資金援助は、後々「特別受益」にあたるとして、他の相続人から不公平だと指摘される原因になります。贈与の都度、贈与契約書を作成し、銀行振込で記録を残すなど、客観的な証拠を確保しておくことが不可欠です。また、特定の相続人にだけ多額の贈与を行うと、遺留分を侵害する可能性もあるため、全体のバランスを考えながら計画的に進める必要があります。
3. 生命保険を活用して「代償分割」の資金を準備する
遺産が不動産など分けにくい資産ばかりの場合に特に有効なのが、生命保険の活用です。被相続人が自身を被保険者とし、特定の相続人(例えば、家を継がない子供)を死亡保険金の受取人に指定しておきます。この死亡保険金は、民法上、受取人固有の財産とみなされ、原則として遺産分割の対象にはなりません。
これにより、家を相続した子供は、保険金を受け取った他の子供に「代償金」を支払う必要がなくなり、スムーズな遺産分割が可能になります。つまり、生命保険を活用することで、不動産を売却することなく、他の相続人の法定相続分に相当する現金を確保できるのです。これは、相続税の納税資金対策としても非常に有効な手段であり、「争族」を避けるための賢い知恵と言えるでしょう。
4. 家族信託を検討し、財産の管理と承継をスムーズにする
近年、新たな相続対策として注目されているのが「家族信託」です。これは、元気なうちに信頼できる家族(子など)に財産の管理・運用・処分を託す契約のことです。遺言書が亡くなった後の財産承継しか定められないのに対し、家族信託は生前の財産管理から死後の承継まで、柔軟に設計できるのが大きな特徴です。
例えば、認知症になって判断能力が低下すると、預金口座が凍結されたり、不動産の売却ができなくなったりしますが、家族信託を組んでおけば、託された家族が本人のために財産を管理し続けることができます。さらに、「自分が亡くなった後は妻に財産を、妻が亡くなった後は長男に」といった、二次相続以降の承継先まで指定することも可能です。遺言や成年後見制度では対応しきれないニーズに応えられる、非常に強力な選択肢です。
5. 【新たな選択肢】中立な第三者(相続手続き代行サービス)に依頼する
遺言書の作成や生前贈与と並行して検討したいのが、相続発生後の手続きそのものを専門家に任せるという選択肢です。特に、相続人同士が直接話し合うと感情的になりがちな場合や、手続きが煩雑で何から手をつけていいか分からない場合に、「相続手続き代行サービス」は大きな助けとなります。
これらのサービスは、司法書士や行政書士などが連携し、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、預貯金や不動産の名義変更まで、一連の煩雑な手続きをワンストップで代行してくれます。専門家が中立的な立場で間に入ることで、冷静な話し合いを促し、手続きの透明性を確保することができます。これは、トラブルを未然に防ぐための、新しい形の予防策と言えるでしょう。
感情的な対立を避け、円満な話し合いを促進
相続手続き代行サービスの最大のメリットの一つは、中立的な第三者が介入することで、感情的な対立を避けられる点です。専門家が相続人全員に対して同じ情報を同時に共有し、法的なルールに基づいて公平な分割案を作成・説明するため、「特定の誰かが情報を独占している」といった不信感が生まれません。財産の話を家族間で直接行う気まずさやストレスから解放され、冷静かつ円満な合意形成をサポートしてくれます。「家族関係を壊したくない」という想いが強い方にとって、非常に有効な手段です。
多忙・遠方の相続人の負担を軽減し、手続きミスを防ぐ
相続手続きは、平日の日中に役所や金融機関を何度も訪れる必要があり、仕事で忙しい方や遠方に住んでいる方にとっては大きな負担です。また、必要書類の不備や申請期限の失念といった手続きミスは、さらなるトラブルの火種になりかねません。代行サービスに依頼すれば、こうした物理的・時間的な負担から解放され、専門家が正確かつ迅速に手続きを進めてくれます。「気づいたらすべて終わっていた」というほどスムーズな進行が期待でき、本業や自身の生活に集中できる安心感は計り知れません。
もし相続でもめてしまったら?冷静に進めるべき3つの対処法
事前の対策を講じていても、残念ながら相続トラブルに発展してしまうこともあります。そんな時、最も大切なのは感情的にならず、冷静に、そして法的な手続きに沿って段階的に解決を目指すことです。当事者だけで話し合っても埒が明かない場合は、問題をこじらせる前に、次のステップに進む勇気も必要です。ここでは、万が一もめてしまった場合に取るべき3つのステップを解説します。
ステップ1:当事者間での「遺産分割協議」
相続が発生したら、まず最初に行うのが法定相続人全員による「遺産分割協議」です。これは、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを話し合って決める手続きです。この段階で円満に合意できれば、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。この協議書は、後の不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きに必要となる非常に重要な書類です。
この話し合いの段階で意見が対立し、まとまらない場合に「相続がもめている」状態となります。感情的な言い争いを避け、お互いの主張を冷静に聞き、妥協点を探ることが重要ですが、それが難しい場合は次のステップに進むことを検討します。
ステップ2:家庭裁判所での「遺産分割調停」
当事者間での話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停は、裁判のように勝ち負けを決める場ではありません。調停委員(通常は民間の有識者2名)が中立的な立場で当事者の間に入り、それぞれの事情や意見を丁寧に聞きながら、解決策を探り、話し合いによる合意を目指す手続きです。
調停は非公開で行われ、当事者が顔を合わせずに済むように配慮されることも多いため、感情的な対立が激しい場合でも冷静に話し合いを進めやすいというメリットがあります。ここで合意に至れば、その内容をまとめた「調停調書」が作成され、これは確定判決と同じ効力を持ちます。
ステップ3:最終手段としての「遺産分割審判・訴訟」
調停でも話し合いがまとまらず、不成立となった場合、手続きは自動的に「遺産分割審判」に移行します。審判では、裁判官がこれまでの経緯や各当事者の主張、提出された資料などを総合的に考慮し、法律に則って「このように遺産を分割しなさい」という最終的な判断(審判)を下します。これは裁判所の命令であるため、当事者はその内容に従わなければなりません。
また、遺言書の有効性や相続人の範囲そのものに争いがある場合は、「遺言無効確認訴訟」や「遺産確認訴訟」といった「訴訟(裁判)」で解決を図ることになります。審判や訴訟は、時間も費用もかかり、家族間の溝を決定的に深めてしまう可能性もあるため、あくまで最終手段と考えるべきでしょう。
相続トラブルは誰に相談すべき?専門家の役割と費用目安
相続の問題は非常に専門性が高く、法律や税金が複雑に絡み合います。トラブルの予防や解決のためには、早い段階で専門家の力を借りることが賢明です。しかし、「弁護士、司法書士、税理士…誰に相談すればいいの?」と迷う方も多いでしょう。ここでは、それぞれの専門家の役割と、相談した場合の費用目安について解説します。状況に応じて適切な専門家を選ぶことが、スムーズな解決への近道です。
弁護士:法的な代理交渉や手続き全般を依頼
相続人同士で既にもめている、またはもめる可能性が高い場合に、まず相談すべき専門家が弁護士です。弁護士は、あなたの代理人として他の相続人と交渉したり、遺産分割協議書を作成したりすることができます。そして、調停や審判、訴訟といった裁判所での手続きの代理人になれるのは、法律上、弁護士だけです。
他の相続人との交渉をすべて任せられるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。費用は「着手金」と「成功報酬」で構成されることが多く、依頼する内容や遺産の額によって変動しますが、着手金で20〜50万円、報酬金で得られた経済的利益の10〜20%程度が一般的な目安です。
司法書士:不動産の名義変更(相続登記)を依頼
遺産に不動産が含まれる場合、必ず必要になるのが法務局での名義変更手続き、いわゆる「相続登記」です。この相続登記の専門家が司法書士です。遺産分割協議が円満にまとまった後の、具体的な手続きを依頼するのに適しています。
司法書士は、遺産分割協議書の作成支援や、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類収集も行ってくれます。ただし、弁護士と違って他の相続人との交渉代理や、調停・審判の代理人になることはできません。あくまでトラブルになっていない円満な相続手続きの専門家と位置づけられます。費用は、不動産の評価額や筆数にもよりますが、登記手続き一式で7〜15万円程度が目安です。
税理士:相続税の申告を依頼
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要になります。この相続税に関する専門家が税理士です。相続税の計算は非常に複雑で、土地の評価や特例の適用など、専門的な知識がなければ適切な申告は困難です。
税理士に依頼することで、正確な申告はもちろん、小規模宅地等の特例などを活用した節税対策についてもアドバイスを受けることができます。相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められており、遺産分割がもめていても延長はされません。費用は、遺産総額の0.5〜1.0%程度が目安とされています。
【費用を具体的に把握】相続手続き代行の料金プラン比較
弁護士、司法書士、税理士といった個別の専門家に依頼するほか、これらの専門家が連携して手続き全体をサポートする「相続手続き代行サービス」を利用する方法もあります。ここでは、一般的な手続きにかかる費用相場を比較してみましょう。
主要な手続きの費用相場比較表
以下は、各手続きを専門家や代行サービスに依頼した場合の一般的な費用相場です。あくまで目安であり、財産の状況や依頼内容によって変動します。
|
手続き内容 |
費用相場(税込) |
主な依頼先 |
|---|---|---|
|
戸籍・住民票などの書類収集 |
約1~3万円 + 実費 |
弁護士、司法書士、行政書士 |
|
遺産分割協議書の作成 |
約5~10万円 |
弁護士、司法書士、行政書士 |
|
銀行口座の解約・名義変更 |
約3~5万円/1金融機関 |
司法書士、行政書士、信託銀行 |
|
不動産の相続登記 |
約7~15万円 + 登録免許税 |
司法書士 |
|
相続税申告 |
遺産総額の0.5~1.0% |
税理士 |
|
フルサポートプラン(手続き全般) |
約20~60万円 |
相続手続き代行サービス、信託銀行 |
まとめ:円満な相続は事前の準備から
相続が「争続」になるのを防ぎ、家族の絆を守るためには、何よりも「事前の準備」が重要です。この記事で見てきたように、相続でもめる原因の多くは、遺産の分けにくさや家族間のコミュニケーション不足、そして準備不足に起因します。
元気なうちに法的に有効な公正証書遺言を作成しておくこと、生前の想いや財産の状況について家族と話し合っておくこと。たったそれだけのことで、残された家族の負担や不安を大きく減らすことができます。もし、何から始めれば良いか分からなければ、まずは専門家に相談してみるのも一つの手です。弁護士や司法書士、税理士、あるいは中立的な相続手続き代行サービスなど、あなたの状況に合った相談先がきっと見つかるはずです。大切な家族がこれからも仲良くあり続けるために、ぜひ今日から「円満相続」への第一歩を踏み出してください。
相続のもめる問題に関するよくあるご質問(FAQ)
Q1. 遺産が預貯金少しと実家だけです。それでも、もめる可能性はありますか?
はい、十分に可能性はあります。司法統計によれば、相続トラブルの約75%は遺産5,000万円以下の家庭で起きています。特に「実家」という分けにくい不動産が遺産の中心である場合、誰が住むのか、売却するのか、代償金はどうするのか、といった点で意見が対立しやすく、トラブルに発展する典型的なケースです。
Q2. 父が「全財産は長男に」という遺言書を書いていました。他の兄弟は従うしかないのでしょうか?
いいえ、従う必要はありません。配偶者や子、親(直系尊属)には、法律で保障された最低限の相続分である「遺留分」があります。この遺言書は遺留分を侵害している可能性が高いため、他の兄弟は長男に対して、遺留分に相当する金銭を支払うよう請求(遺留分侵害額請求)することができます。遺言書があっても、内容が不公平であればトラブルの原因になります。
Q3. 兄弟仲が悪く、直接話し合いができません。どうすればよいですか?
当事者間での話し合いが困難な場合は、第三者を介することをおすすめします。まずは弁護士に相談し、代理人として交渉してもらうのが一つの方法です。また、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てれば、調停委員が間に入って中立的な立場で話し合いを進めてくれます。感情的な対立を避けるためにも、問題を抱え込まずに専門機関に相談することが重要です。
Q4. 専門家に相談したいのですが、費用が心配です。どのくらいかかりますか?
費用は依頼する専門家や内容によって大きく異なります。例えば、不動産の名義変更(相続登記)だけなら司法書士に7〜15万円程度で依頼できます。すでにもめていて交渉や調停を依頼する場合は弁護士に相談し、着手金として20〜50万円程度かかるのが一般的です。多くの事務所では初回無料相談を実施しているので、まずは複数の専門家に相談し、見積もりを取ってから比較検討することをおすすめします。